- 特集
- 2025.08.21
妊娠中に離婚した場合の親権と養育費について

男性女性を問わず妊娠中の離婚を考えている方にとって、子どもの戸籍や親権、経済的な問題など、疑問や不安は多くあると思います。妊娠中でも離婚は可能ですが、法律上の手続きや、デメリット・リスクを理解し、慎重に進める必要があります。
本記事では、妊娠中に離婚する際のポイントや注意点について、特に手続面から、弁護士が詳しく解説します。
目次
1. 妊娠中でも離婚はできる?
妊娠中の離婚を禁止する法律はなく、妊娠中でも法律上は離婚することが可能です。
※離婚の方法には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」がありますが、それぞれの詳細については別のコラム<産後離婚する場合の注意点を解説! | KTG>をご参照ください。夫婦が合意すれば離婚届を提出することで協議離婚が成立します。一方で、合意が得られない場合には、家庭裁判所での調停や裁判によって離婚を目指すことになりますが、これらの場合には必ずしも離婚できるわけではありません。
ただし、あくまで一般的にですが、妊娠中はホルモンバランスの変化等により感情的になることもあるといわれます。そのため、女性側が離婚を検討している場合には、一時的な感情によるものなのか冷静に判断することが大切であるといえます。また、男性側が離婚を検討している場合には、妊娠による影響を理解したうえで、離婚を切り出すことやそのタイミングについて十分に検討することが重要であるといえます。
さらに、妊娠中であることから、生まれてくる子どもの将来を見据えることも必要となるため、その観点からも慎重な判断が求められるといえるでしょう。
2. 妊娠中に離婚した場合の親子関係はどうなる?
妊娠中に離婚した場合、子どもが生まれてくる頃には父母は別居していることが多いといえますし、離婚前の夫婦の関係性などから親子関係に疑問が生じることもあります。
これは主に父親と子どもとの関係で問題となります。というのも、母親の場合は、妊娠や出産の事実があれば、
(血縁上も法律上も)生まれてきた子どもと母子関係があるといえるからです。
※ただし、卵子提供や代理懐胎の場合など、必ずしも明らかと言えない場合もあります。
一方で、父親と子どもの関係については、血縁上・生物学上の親子関係と法律上の親子関係が異なることがありえます。
血縁上の親子関係とは、文字どおり血が繋がっていることを指しますが、生まれてくる子どもに対してすべからくDNA鑑定などをすることは現実的ではありません。そのため、法律上は、一定の事実があれば父と子の親子関係を推定する形式を採っています。
具体的には、以下の事実があれば、父と子どもには法律上の親子関係があるものとみなされることになります。
①結婚している間に妻が妊娠した場合
※結婚した日から201日以降に生まれた子どもや、婚姻解消日・婚姻取消日から300日以内に生まれた子どもも、結婚している間に妊娠したとみなされます
②結婚前に妊娠した子どもが結婚後に生まれた場合
※結婚した日から200日以内に子どもが生まれた場合も、結婚前に妊娠したとみなされます
重要なのは、民法上の父子関係は、母子関係とは異なり、あくまで推定であるという点です。
そのため、父子関係については、上述した事実(結婚期間中の妊娠など)があったとしても、推定を覆すような事実があれば否定されることもあります。例えば、妊娠したのが結婚期間中であったとしても、その期間に夫が長期海外出張に行っており家にいなかった場合などは、夫と生まれてくる子どもとの間に血縁上の父子関係があることはないでしょう。
しかしながら、このように父子関係がないことが明らかな場合であっても、法律上は(元)夫と子どもとの間に父子関係があるものと推定されてしまいます。このような場合にも、法律上の親子関係が覆せないとなると、事実に合わない法律関係が発生することになってしまいます。そのため、民法ではこのような場合に備えて、推定を覆すための手続が用意されています。
※一方で、母子関係は妊娠や出産という事実によって決められることが多いため、これを否定することは難しいかと思います。
父子関係の推定を覆したい場合には、「嫡出否認の訴え(民法第774条)」という手続を行う必要があります。これは、父親と推定された者が、家庭裁判所に対して、生まれてきた子が「自分の子ではない」と主張する手続です。この手続は、子どもの出生を知った日から3年以内に提起しなければなりません。
3. 妊娠中の離婚で子どもの親権はどうなる?
親権とは、子どもの日常生活の世話や教育をする権利(「身上監護権」といわれます。)と、子どもの財産を管理したり契約を代理したりする権利(「財産管理権」といわれます。)を合わせた権利といえます。
婚姻中であれば、通常は夫婦が共同して親権を行使することになりますが、日本の法律では、離婚後の親権はどちらか一方の親しか持つことができません。そのため、離婚する際に子どもの親権者を決めなければならず(民法第819条1項2項)、離婚届にも未成年者についてどちらが親権者となるのか記載する欄があります。
さて、親権者の決め方ですが、出産後の離婚、すなわち子どもがすでに生まれている場合には、離婚する際に話し合ったり、裁判所を通じた手続で親権者を決めることになります。
一方で、妊娠中の離婚では、まだ子どもが生まれる前のため、離婚時点で親権者を決めることはできません。この場合には、子が生まれた後に親権者となるのは、原則として母親とされています(民法819条3項)。ただし、話合いや裁判所を通じた手続により父親が親権者となることもできます。
4. 妊娠中の離婚と子どもの戸籍
さらに難しくなりますが、出生時に両親が離婚していた場合には、子どもはどの戸籍に入るのでしょうか。
※こちらについては<コラム:戸籍制度と離婚について | KTG>もご参照ください。重要な点として、子どもは必ずしも親権者と同じ戸籍に入るわけではないことが挙げられます。
4-1. 出生届の提出
子どもが生まれた場合には、「出生届」という書類を役所に提出しなければなりません。出生届を提出することで、はじめて子どもは(親の)戸籍に入ることができます。戸籍がない場合(いわゆる無戸籍者)のデメリットは本稿では詳述しませんが、子どもにとって非常に重要な手続となります。
さて、この出生届は、14日以内に役所に提出する必要があります。
提出する人は、両親が結婚している場合には、両親のいずれかが提出します(両親による提出が難しい場合の例外もあります)。
一方で、離婚後に子どもが生まれた場合は、母親が提出しなければなりません(戸籍法49条1項、52条1項。母親が提出することが難しい場合の例外規定もあります。)。
4-2. 子どもの戸籍
出生時に両親が離婚していた場合には、生まれてきた子どもの出生届は母親が役所に提出しなければならない旨を前述しました。そうすると、子どもは、出生届を提出した母親の戸籍に入るようにも思えますが、実は必ずしもそうはなりません(むしろそうならないことの方が多いといえます)。以下ではケースごとに詳しく説明します。
(1)元夫の子どもであると推定される場合
まず、①結婚している間に妻が妊娠した場合や、②結婚前に妊娠した子どもが結婚後に生まれた場合などは、法律上は、その後に夫婦が離婚したとしても、元夫の子どもであると推定されます。
そして、元夫の子であると推定される場合には、夫婦の離婚の有無にかかわらず、子どもは「離婚の際における父母の氏を称する」(民法790条1項)とされています。
「離婚の際における父母の氏」とは、父母が結婚していたときに名乗っていた氏(=筆頭者の氏)のことを指します。
この規定があるため、子どもは、父母の離婚後に生まれた場合であっても、まずは、父母が結婚していたときの筆頭者の戸籍に入ることになります。
したがって、離婚後に生まれた子どもは、必ずしも親権者や母親の戸籍に入るわけではありません。(ただし、父母の結婚時の筆頭者と親権者が一致する場合や、筆頭者が母親であった場合には、結果的には親権者や母親の戸籍に入ることもあります。)
(2)子どもの戸籍を、元夫の戸籍から母親の戸籍に移す方法
上述のとおり、母親が親権を持っていたとしても、子どもは自動的には母親の戸籍に入らず、まずは結婚時点の筆頭者(現在の日本では95%近くが夫)の戸籍に入ることになります。そのため、親権者が母親である場合には、同居しているにもかかわらず、母親と子どもの苗字が異なる等の事態が生じることになります。
このような事態を解消するには、子どもを父親の戸籍から母親の戸籍に移す必要があります。そのための手続として、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立て」を行い、その許可を得た後に市区町村役場で「入籍届」を提出する必要があります。
(3)元夫の子どもであるとの推定が及ばない場合
さて、離婚後に元妻が子どもを妊娠した場合などには、元夫については父子関係の推定が及びません。また、妊娠の時期と離婚の前後が不明な場合であっても、離婚後300日を過ぎて生まれた子どもは、元夫の子どもとは推定されません。
このような場合には、法律上当然には元夫と生まれてくる子どもとの間に父子関係は認められないため、(何もしなければ)子どもが元夫の戸籍に入ることはありません。子どもは、父子関係が不明である以上、親子関係が明らかである母親の戸籍に入ることになります。
(4)認知と戸籍
父親と子どもとの間に、法律上の父子関係の推定が及ばない場合(例えば婚外子や離婚後300日を過ぎて子どもが生まれた場合)に、父親が子どもを認知したらどうなるでしょうか。
認知とは、父子関係の推定が及ばない子どもに対して、(法律上)自身の子どもであると認めることといえます。認知がされた場合には、父親と子どもとの間に法律上の親子関係が生じることになります。
そして、父子関係が推定されない子どもは、父親が認知をした場合であっても、上記(2)の場合と同じように、まずは母親の戸籍に入ることになります。
※認知された子どもは、このようにまずは母親の戸籍に入ることになりますが、その後に認知した父親の戸籍に移ることが否定されているわけではありません。
「子の氏変更の申立」等の手続により、場合によっては戸籍を移ることが可能であることもあります。
5. 妊娠中の離婚とお金
離婚をするときに決めることについては、<コラム:産後離婚する場合の注意点を解説! | KTG>のとおりです。本稿でも説明した親権のほかにも様々なことを話合いや裁判所を通じて決めていかなければなりません。
以下では、離婚時に決めなければならないことのうち、特に妊娠中の離婚で留意すべき点に限定して説明します。
5-1. 養育費
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことで、具体的には生活費や教育費などがこれにあたります。養育費は、子どもの親であることから当然に生じる義務とされており、これは離婚の有無や子どもとの同居の有無、子どもの親権の有無に関係なく生じます。
基本的には、親権を持たない親が自身の分担部分を、親権を持つ親に支払う形となります。また、養育費の金額は、父母双方の収入や生活状況によって決まります。
さて、妊娠中に離婚した場合であっても、離婚後300日以内に生まれた子どもは、元夫の子どもと推定されます。そして、離婚後に子どもが生まれた場合には、原則として親権は母親が有することになります。
そのため、妊娠中に離婚した場合には、多くの場合において、父親が母親に対して子どもの養育費を支払う形になるといえます。
一方で、離婚後300日を過ぎて生まれた子どもは、父親の子どもとは推定されません。そのため、この場合には、父親には当然には養育費の支払義務は発生しません。ただし、父親が自らの子であると認知した場合(裁判手続による場合も含みます。)には、法律上の親子関係が生じるため、養育費の支払義務が生じます。
5-2. 財産分与
離婚に伴い、夫婦が婚姻期間中に築いた財産は「財産分与」の対象となります(民法768条)。財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を公平に分配するという考え方に基づいていますので、分与の割合は原則として「2分の1ずつ」とされています。
もっとも、貢献度や特別な事情によって調整されることもあります。なお、協議で合意できない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決定されることになります。
妊娠中の離婚であれば、子どもが生まれてくる女性側が多く分与されそうにも思われますが、基本的には上述のルールに則って双方が2分の1ずつ取得することになります。
財産分与はあくまで婚姻中の財産の分配であって、子どもの養育にかかる費用は養育費で考慮するというすみ分けがなされているともいえます。
5-3. 慰謝料
離婚と併せて慰謝料が請求されることがあります(民法709条)。
※難しい話をすれば、離婚の際に請求される慰謝料としては、離婚自体慰謝料と離婚原因慰謝料の区別などもありますが、ここでは割愛します。いずれにせよ、慰謝料が認められる典型的な場合は、不貞行為やDVがあったことなどが挙げられます。
さて、本稿との関係では、妊娠中に離婚を切り出したのが男性側の場合、女性側が、妊娠中にもかかわらず離婚されたことをもって慰謝料を請求できるかが問題となります。結論から申し上げますと、「離婚したのが妊娠中であった」という事実のみをもって慰謝料を認めてもらうことはとても難しいといえます。
もっとも、一般的に、離婚の際に慰謝料請求が認められるか否か、また認められる場合にいくら認められるかは、様々な要素が総合的に考慮されて判断されることになります。そのため、妊娠中の離婚の態様によっては、慰謝料が増額される事情になることはありえます。
なお、慰謝料が認められるためには証拠が必要となるため、しっかりと集めて準備をしておく必要があります。
6. まとめ
本稿では、妊娠中に離婚する場合の法的な手続などについて解説してきました。特に、子どもの戸籍に関しては非常に複雑です。
子どもがまだ生まれていない状態での離婚のため、男性女性とも、なかなか離婚後のイメージが湧きづらいこともあるかと思います。
妊娠中の離婚においては、信頼できる専門家や周囲のサポートを得ながら、慎重に判断することが大切です。
是非一度弁護士法人KTGにご相談ください。



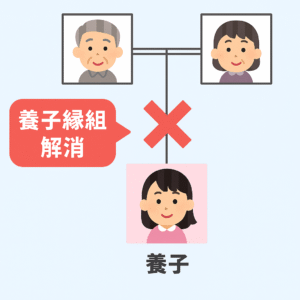
離婚手続きと支払われるお金-_-その他暮らし-_-ファイナンシャルフィールド.jpg)