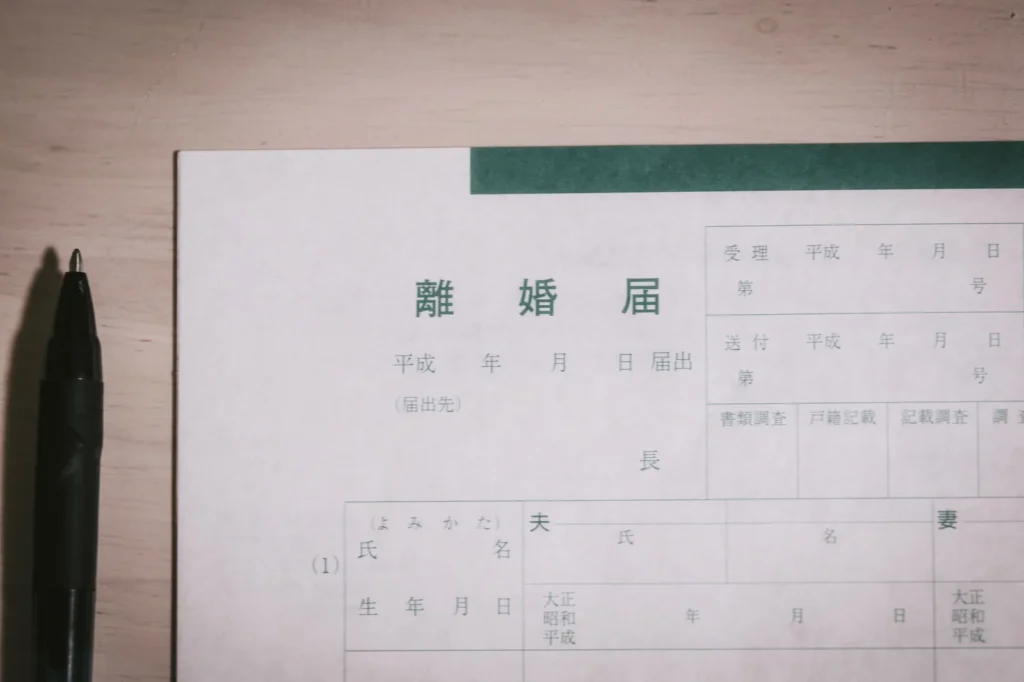- 特集
- 2025.05.08
相続トラブルを防ぐ!遺産分割協議の流れと注意点
_ファイナンシャルフィールド__相続税.jpg)
前回のコラムでは、遺言と相続や、法定相続人の範囲や順位について解説しました。
遺産相続は、「争族」とも揶揄されるほど親族間でのトラブルが絶えないテーマです。
思わぬ対立や誤解、感情的なもつれが生じ、話合い等が難航するケースも少なくありません。
本記事では、遺産分割協議の基本的な流れや注意点、法定相続分の考え方、そしてトラブルが起こりやすいポイントについて解説します。相続でもめないために、そして円満な手続きを行うために、知っておくべき知識を押さえておきましょう。
目次
1. 遺産分割協議の流れ
当事者の話合いである遺産分割協議とはどのような流れで進むのでしょうか。
ドラマでは言い争いをしているシーンが印象的ですが、実際にはその前後も非常に重要となります。
1-1 当事者の確定
まず、遺産分割協議を始める前に当事者を確定しなければなりません。
前回のコラムで述べたとおり、一部の法定相続人が欠けた状態で行った遺産分割協議は無効となってしまうため、当事者の確定は非常に重要であるといえます。
1-2 遺産の正確な把握
また、遺産についても、すべての相続人が、(できる限り)正確に把握する必要があります。遺産分割協議で話し合っていない遺産が協議の後に判明した場合には、その遺産について再度遺産分割協議をしなければなりません。
協議を迅速に終わらせるためにも、自身が把握している遺産を全て共有することが大切です。
1-3 協議の内容
遺産分割協議で話すことは、被相続人の遺産のうち、
①何を(どれくらい)、
②誰が、相続するか
というものになります。
文字通り、遺産を分割する話合い、ということになります。
最終的に相続人の全員が同意できるのであれば、話合いの方法(当然ですが脅迫等の犯罪行為は除きます。)や頻度、分割の内容も、基本的にはどのような形でも構いません。
実際には感情的な対立になることも多いため、各相続人が誠意をもって対応することが大切であるといえます。
1-4 遺産分割協議書の作成
そして、最後に、話合いがまとまったら、必ず「遺産分割協議書」という形で、話合いの結果を書面に残しておきましょう。言った言わないの紛争を避ける意味でも重要ですが、(遺言書がない場合には、)遺産分割協議書がないと、被相続人の銀行口座の解約や不動産の登記の変更ができないため、対外的に動けなくなってしまいます。
2. 法定相続人が相続する財産の割合(法定相続分)
民法では、誰が当事者(法定相続人)に該当するかに加えて、各法定相続人が相続できる遺産の割合が定められています。それが、「法定相続分」といわれるものです。
各法定相続人の相続割合を以下に記載しますが、重要なのは、遺産分割協議では、当事者(法定相続人)の全員が同意していれば、基本的にどのような分割割合でも認められる点にあります。全員が同意していれば、誰か一人が(遺留分を除き)すべての遺産を相続することもできますし、任意の割合で分割することも可能です(本稿では割愛しますが、被相続人の負債は例外です。)。
すなわち、民法が定める相続分よりも、当事者全員が同意した相続割合の方が優先されることになります。
とはいえ、法定相続分は、当事者が話し合う際のベースやガイドラインになりますし、法定相続分どおりの分割で全員が同意することも多いかと思います。
また、仮に話合いが不調に終わり、後述する調停や審判になった場合、裁判所が各相続人の相続割合を決める基礎になるものです。
※ただし、調停等でも、必ずしも法定相続分どおりの分割がなされるわけではありません。特に、寄与分や特別受益といった主張がなされる場合には、法定相続分から変わる可能性があります。
そのため、基本である法定相続分を押さえておくことは重要であるといえます。
2-1 配偶者と第一順位(直系卑属:子など)が相続する場合(民法第900条1号)
・配偶者:1/2
・第一順位:1/2(複数いる場合は均等に分配)
この場合は、配偶者と第一順位が、それぞれ1/2ずつ相続します。
配偶者は、重婚が認められていない日本では必ず1名となりますので、同人が単独で1/2を取得します。一方で、第一順位については、全体の1/2の遺産を、さらに第一順位内で(家系ごとに均等に)分けることになります。
例えば、被相続人に、配偶者1名と子2名がいた場合、配偶者は1/2の相続となります。一方で、子はそれぞれ1/2×1/2(2名均等の2分割)=1/4ずつの相続となります。
気を付けなければならないのが、第一順位内の均等割りは、代襲相続が発生している場合でも、被代襲者を基準として行わなければならない点です。
具体例として、被相続人に、配偶者Aと子B・Cがおり、Cは先に亡くなっているため孫D・E・Fが代襲相続したという場合を考えてみましょう。この場合、配偶者Aは常に1/2を取得することになります。そして、第一順位全員の合計取得分も1/2となります。その後の分け方ですが、第一順位のBとD・E・Fの4名で人数割り(1/2×1/4で各8分の1ずつ)というわけではありません。
この場合、もともとの法定相続人はBとCであり、D・E・FはCの代わりとしてCの取得分を代襲しているため、あくまでもともとの法定相続人をベースに計算します。
①まずは被代襲者をベースに法定相続分を割り出します。この場合はBとCがそれぞれ、1/2×1/2(BとCの人数割り)で1/4の取得分を持っていると考えます。
②次に、Cについては、代襲相続が発生しているため、代襲相続人であるD・E・Fの3名でCの取得分を人数割りすることになります。すなわち、1/4(Cの取得分)×1/3(代襲相続人の人数割り)で、各1/12ずつを取得することになります。
まとめると、具体例のケースだと、
・配偶者A :1/2
・子B :1/4
・孫D・E・F:各1/12ずつ
となります。
代襲相続については、法律コラム「相続の基本を徹底解説!法定相続人の範囲・順位・相続割合までわかりやすく説明」をご参照ください。
2-2. 配偶者と第二順位(直系尊属:被相続人の親など)が相続する場合(民法第900条2号)
・配偶者:2/3
・第二順位:1/3(複数いる場合は均等に分配)
この場合は、配偶者が2/3、第二順位が(全員合わせて)1/3を相続します。
また、上で述べた第一順位の場合と同様に、第二順位の法定相続人が複数名いる場合は、その方々で1/3をさらに均等割りします。
なお、第二順位については、前回のコラムで述べたとおり、その親等の尊属が一人もいない場合にのみ、さらに上の尊属にさかのぼる点に注意が必要です。
例えば、法定相続人が配偶者と被相続人の母方祖母の場合(被相続人に子がおらず、父母と父方の祖父母、母方の祖父がすでに亡くなっている場合)には、配偶者が2/3、母方祖母が1/3を取得します。この場合、父方の曽祖父母がご存命でも相続することはできません。第二順位としては、親等が近い母方祖母が単独で相続することになります。
2-3. 配偶者と第三順位(兄弟姉妹(甥姪))が相続する場合(民法第900条3号)
・配偶者:3/4
・兄弟姉妹:1/4(複数いる場合は均等に分配)
この場合は、配偶者が3/4、第三順位が(全員合わせて)1/4を相続します。第三順位の法定相続人が複数名いる場合に、その方々で1/4を均等割りすることはこれまでと同様ですが、一点例外があります。いわゆる半血兄弟姉妹といわれる方々です。
兄弟姉妹の相続分は、父母の両方を共通に持つ場合(全血兄弟姉妹)と、片方の親のみ共通の場合(半血兄弟姉妹)で異なり、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の相続分の1/2となります(民法第900条4号)。
具体例をあげると、被相続人の法定相続人が、配偶者A、被相続人と父母が同じの兄B、父が同じで母が異なる弟C、母が同じで父が異なる妹Dがいた場合を想定します。この場合、まずはAが3/4を取得します。残りの1/4をB・C・Dで分けることになりますが、Bは全血兄弟、CDは半血兄弟姉妹のため、分ける比率は、B:C:D=2:1:1となります。したがって、Bは1/4×2/4で1/8、CとDは1/4×1/4で1/16ずつ取得することになります。
なお、第三順位の代襲相続は一度しか(甥姪までしか)認められていないことは前述のとおりです。
2-4. 子どもや直系尊属・兄弟姉妹のみが相続する場合
配偶者がいない場合です。
これらの場合は、第一順位がいれば第一順位のみが、いなければ第二順位のみが、第一順位も第二順位も該当する方がいなければ第三順位のみが相続することになります。
配偶者の相続分がないため、該当する順位の方々が100%を取得することになりますが、同順位内に複数名がいる場合には、これまで述べたところと同様に、それぞれ均等に分配されます。
3. 遺産分割協議で揉めやすいポイント
さて、前回と今回のコラムでは、遺産分割協議を念頭に、法定相続人や法定相続分について述べてきました。
話合いの当事者になれる人は民法に定められており(法定相続人)、当事者が集まって遺産の分け方について話し合うことが遺産分割協議でした。遺産分割協議では、全員が同意していればどのような分け方も基本的には認められますが、ガイドラインとして民法で各々の取り分が定められています(法定相続分)。
全ての話合いが法定相続分に沿って行われ、全員が納得してまとまるのであれば、遺産の紛争は起こりませんが、現実にはそうならないこともあります。
まず、法定相続分に争いはないものの、具体的に相続する内容で争いになることが考えられます。というのも、遺産と一言でいっても、現金や預貯金もあれば、土地や建物、車や株式などもあります。すべて現金に換価して各相続人に分けるのであれば問題は生じませんが、現実には、「遺産のうち不動産が欲しい」等で具体的に相続したい遺産が競合したりする場合もあります。
すべてが(細かく分割できる)現金でない以上、厳密に分割できない場合もあるし、価格の評価で争いになることもあります。
また、法定相続分での分割についても争いになることがあります。
例えば、被相続人のご生前の事業を手伝って資産(遺産)を増やすことに尽力した息子Aと、被相続人と疎遠だった息子Bがいた場合、遺産を増やしたAからすれば、何もしてないBが自分と同じ取り分で遺産を相続するのには、なかなか納得するのが難しいのではないでしょうか。
また、被相続人の生前に、被相続人から長年にわたり生活費の援助を受けていた娘Cと、早くに自立して援助を一切受けていなかった娘Dがいた場合、やはりDからすれば、Cが自分と同じ取り分で遺産を相続するのは納得するのが難しいこともあるかと思います。
詳しくは割愛しますが、相続人の間で法定相続分で分けることが不公平な結果になるといえる一定の場合には、民法によって、各々の取り分が修正されることがあります。「寄与分」や「特別受益」といわれるものです。
もっとも、寄与分や特別受益が認められない場合であっても、被相続人との距離感や生前の態度、また相続人同士の関係性から、話合いがまとまらないことは多くあります。
4. 遺産分割協議がまとまらなかった場合は
4-1. 弁護士に依頼する
当事者だけで話し合うと、感情の対立や不信感などから話がまとまらないことがあります。このような場合には、一方が代理人として弁護士を立てると解決することがあります。感情の対立は、当事者同士が直接話すことが原因となることもあるため、弁護士が一方を代理することでこれを避けることができるためです。
また、不信感に関しても、相手方の気持ち次第ではありますが、専門家が入れば一定程度緩和されることも多いかと思います。
4-2. 遺産分割調停
当事者間で話合いがまとまらないときは、当事者ではない人が間に入って双方の主張を調整することも考えられます。
もっとも、ある相続人の配偶者や友人が間に入ると、客観性や公平性が問題となり、かえって対立が深まる事態にもなりかねません。
そのため、間に入る人は中立な立場から判断することが重要となりますが、そのためには裁判所手続を用いることが考えられます。
裁判所手続としては、「遺産分割調停」と「遺産分割審判」があります。
「遺産分割調停」は、裁判官と調停委員(民間から選出される方々)が、当事者の間に入って、それぞれの話を聞き、当事者が納得できる解決を目指す手続です。
調停で目指すのは当事者の同意となります。そのため、当事者に納得できずに同意しない方がいる場合には、(基本的には)調停は成立しません。この場合には、次に記載する「遺産分割審判」を検討することになります。
※全員の同意が得られない場合でも、一定の場合には、裁判所が職権で判断を下すことがあります。「調停に代わる審判」と呼ばれるものですが、同意が得られない理由が些細なものである場合や、感情のみが対立している場合などに行われるものとなります。
4-3. 遺産分割審判
前述した調停は、あくまで調停委員を通じた話合いをし、その結果として当事者の同意を目指す手続でした。そのため、当事者に同意しない人がいる場合には、原則として調停は成立しません。
一方で、「遺産分割審判」では、話合いの要素はほとんどありません。審判は、当事者が主張や証拠などを出し合い、これらを基に裁判所が判断を行う、という構造になっています。すなわち、当事者の納得や同意は関係なく、裁判所が適切だと思う判断が下されます。
5. まとめ
本稿では遺産分割における原則を述べてきましたが、本稿に記載できなかった例外もあります。遺産分割を納得して進めていくためには、事前に十分な知識を持つことが重要です。
スムーズな相続手続きを進めるためにも、専門家である弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。KTGグループでは弁護士の他、同グループに司法書士・税理士・社会保険労務士等様々な資格保有者が在籍しております。各士業間で案件を共有し、連携を図ることにより、適切かつ迅速に案件を処理することができます。
相続でお悩みの方は是非一度、弁護士法人KTGまでお気軽にご相談ください。